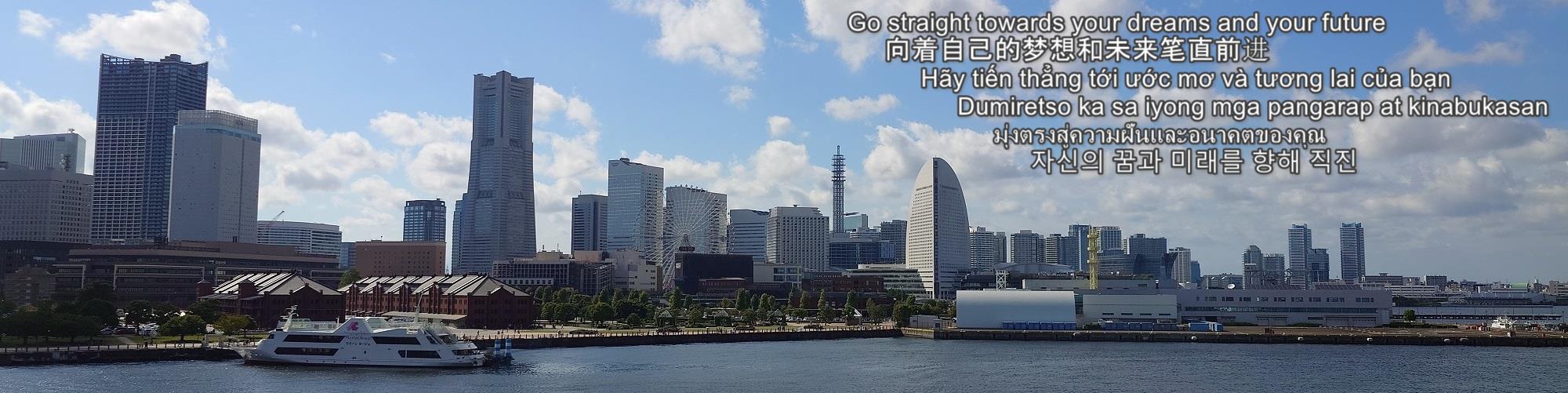入国/在留資格申請
日本で働きたい、日本で暮らしたいという外国人の方々のサポートを致します。
主な取り扱い業務
- 在留資格認定証明書交付申請(外国人を日本に呼び寄せる)
- 在留資格変更許可申請(例:「留学」→「就労」など)
- 在留期間更新許可申請(ビザの延長)
- 永住許可申請(日本に長く住む方のための手続き)
- 帰化申請サポート(日本国籍取得を目指す方へ)
人は生まれた際に、どのように国籍が決まるのでしょう。親の国籍でしょうか、生まれた場所でしょうか。
日本の場合、「父母両系血統主義」といい、父または母のいずれかが日本国籍の場合には、生まれた場所を問わずに日本国籍を付与するものとされます。国籍法は過去に何度か改正されており、1984年の改正以前は、「父系血統主義」となっていました。「父系血統主義」とは、父親が外国籍であった場合には、例え母親が日本国籍であったとしても、子供は自動的には日本国籍とならないとするものでした。
一方、その領土で生まれた者に対してはその国の国籍を与えるという「生地主義」があります。生地主義の場合には、「ただし自国外で生まれた場合でも、両親のいずれかが自国民であれば、自国の国籍を付与する」のように、補充的に血統主義を採用していることが多いです。
日本のような父母両系血統主義を採用している国として、中国、韓国、タイ、フィリピン、インド、ドイツ、フランス、イタリアなどがあります。また、イスラム系の国々では、かつての日本のような父系血統主義を採用している国が多く見られます。
一方で、アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランドなどの国は生地主義を採用しています。
帰化とは、日本国籍を付与されることです。これに伴って、母国の国籍を喪失することになります。一方、永住権(在留資格「永住者」)の場合、日本国籍を取得することはなく、母国の国籍を継続して保有することになります。
帰化のメリットとしては、以下のような点があげられます。
①日本国籍が付与されることで、日本のパスポートを取得することができます。日本のパスポートは、ビザなしで渡航できる国が多い点が特徴としてあげられます。
②就労活動の制限がなくなる点においては、永住権も同様ですが、日本国民となることで、国家公務員となることができるようになります。
③選挙権や、被選挙権が与えられます。
④海外へ渡航する場合の再入国許可/みなし再入国許可が不要になります。また、日本国民になり外国籍を失うため、何らかの理由により退去強制処分になることもありません。
在留資格「永住権」を取得した場合、以下のような取扱いとなります。
1.母国(外国籍)を保持したまま、日本に安定して滞在し続けることができるようになります。他の在留資格と異なり、失業や離婚・死別した場合でも、在留資格が失われることはありません。
2.在留期間が無制限となるため、在留資格の更新手続きが不要となります。(在留カードの更新は7年毎に必要となります)
3.就労制限がありません。どのような職業に就くことも認められます。
4.配偶者や子供の永久許可申請要件が緩和されます。(原則10年→1年)
5.住宅ローンが組みやすくなります。
では、永住権取得のための要件はどのようなものでしょうか。これには、次のような審査基準が設けられています。
1.素行が善良であること
帰化申請における素行善良要件と類似しています。犯罪歴、交通違反歴などが確認されます。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
帰化申請における独立生計要件と類似しています。本人あるいは世帯の収入で、安定した生活が営めるかという観点で審査されます。目安として、年収が過去5年間にわたって300万円以上(1名につき)であるかどうかになります。また、扶養家族が居る場合には、扶養家族1名につき、+50万円が目安となります。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
国益要件といい、申請人が日本国の利益に合うかどうかという点になります。さらに具体的には、次のようなものになります。
①日本に引き続き10年以上在留し、うち5年以上は就労資格を以て就労していること
3か月以上日本を離れていた期間があったり、年間100日以上日本を離れているような場合には、「引き続き在留している」とはみなされない可能性が高くなります。また5年の就労についても途中で転職していても問題ありませんが、アルバイト等ではなく、また期間を空けずに、5年間継続して就労していることが求められます。
②納税義務等公的義務を履行していること
税金、年金、社会保険等を滞納、遅滞なく支払っていることが要件となります。特に、納期限を守って支払っているかが重要となります。結果的に支払いを行っている場合でも、延滞が見受けられる場合には、マイナス要素として判断されます。もし、延滞が発生してしまっているような場合には、延滞せずにきちんと納めた実績を2年以上は継続するようにしましょう。また、過去の延滞において特別な事情があった場合には、その事情と、再発防止策について理由書に記載することで、許可される可能性も十分にあります。(例えば、母国の家族の入院のため一時帰国しており、税金を納める機会を逸してしまったこと、再発防止策として、自動引き落としにした結果、これ以後の延滞は発生していないことなどを説明すること)
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
最長の在留期間といった場合、「5年」がこれに該当するのですが、現時点では、「3年」となっている場合には、最長であるとみなされるように運用されています。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。これは、薬物中毒や、感染症などに罹患していないことを表します。
⑤身元保証人がいること。これは、借金の連帯保証人のようなものではなく、一種の道義的責任のため、永住権を取得した申請人が後に法令違反を行った場合でも、何らか法的な責任を問われるものではありませんが、今後その他の永住許可申請における保証人としての資格はなくなるでしょう。
永住権の許可要件として、「日本に引き続き10年以上在留し、うち5年以上は就労資格を以て就労していること」がありますが、次のような一定の場合には、その条件が緩和されます。
①日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合には、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合には、引き続き1年以上日本に在留していること。
②定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
③高度専門職令に規定するポイント計算で、3年前から70点以上のポイントを有していることが認められる場合:10年→3年
④高度専門職令に規定するポイント計算で、1年前から80点以上のポイントを有していることが認められる場合:10年→1年
永住許可申請における注意点を掲げます。
1.転職について
過去に転職歴がある、あるいは、永住許可申請中に転職を行う場合について、転職自体に問題はないのですが、例えば転職によって収入が減少してしまっていたり、何度か転職を繰り返しているような場合には、「収入が安定していない」とみなされる可能性があります。転職を行った場合には、転職後1年程度は安定した収入の得たという実績を積んでおくのが良いでしょう。また、永住許可申請中には、あまり転職は行わない方が無難かもしれません。
2.扶養家族について
扶養家族が居る場合の独立生計要件については、「永住権の基本」(2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること)に記載しましたが、もう1点、そもそもの扶養家族の範囲は適正か?という問題があります。例えば、海外居住の親族まで扶養家族とした上で、住民税を非課税にしているような場合、実は海外の扶養家族には所得があり、扶養家族としては不適正であったような場合には、不正行為としてみられる可能性が高いです。このようなケースに該当する場合には、ただちに是正を行っておく必要があります。
3.オーバーワーク
申請人がオーバーワークしていないことは当然のことながら、周辺の親族についても、オーバーワークとなっていないか、注意する必要があります。留学生、家族滞在等の場合には、1週間に28時間という時間制限があるため、この制限を超えてしまっている場合には、ただちに是正を行った上で、5年程度は適正な状態であるという実績が必要になります。
4.経営者/事業主の場合
申請人や親族が、経営者/事業主である場合には、さらに幾つかの注意点があります。
①経営する会社の安定性や継続性が審査されます。債務超過となっていないか、赤字決算となっていないか等、安定した事業運営となっていることが求められます。その意味では、2年程度の安定した経営実績(黒字決算)が求められます。
②経営者の場合、事業税など会社としての税金を納めていることや、各種社会保険への加入、支払いを適正に行っていることが求められます。
5.現在の在留資格の有効期限と特例期間について
通常の在留資格の更新や変更を申請する場合、その現在の在留資格の有効期限が迫っている場合でも、有効期限前に申請を行うことで、申請中の資格が認められるまでは引き続き有効であるという特例期間の制度があります。
特例期間:在留期限が過ぎる前に在留期間更新(変更)許可申請を行った場合は、その申請結果が出るか、あるいは有効期限から2か月を経過するまでは、引き続き在留を続けることが許されるという制度
しかし、永住権の申請の場合には、この特例期間の適用はありませんので、現在の在留資格の有効期間が十分でるか確認した上で(あるいは、更新を行った上で)、永住権の申請に望む必要があります。
帰化には、大きく分けて3種類があります。
①普通帰化
②簡易帰化
③大帰化
①の普通帰化は、国籍法の5条に列挙されている要件を満たす場合に認められる帰化となります。「日本に引き続き5年以上住んでいること」「18歳以上であること」「素行が善良であること」「独立して生計を営めること」など、幾つかの条件があります。
これに対して、②簡易帰化とは、国籍法5条の普通帰化の要件を満たさない場合でも、帰化が認められる場合があるものになります。例えば、「日本で生まれた」「配偶者が日本人」「親が日本人」など、一定の要件に当てはまる人について、日本での住居年数や、年齢制限、独立生計要件などが緩和、免除されることになります。
③大帰化とは、国籍法9条に規定されており、「日本に特別の功績のある外国人」が要件となっていますが、今までこの大帰化で申請を行った例は1件もありません。
普通帰化の要件は、国籍法の5条1号~6号で定められています。概ね以下のような要件になりますが、以下の要件を外観上満たしているとしても、帰化を認めるかどうかは、法務局の裁量によるところがあるため、これ以外の要素や、帰化を希望する外国人の個々の事情・背景によっても、判断が異なることがある点に留意が必要です。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
原則的5年間継続して日本に住居していることが条件となります。海外へ渡航してはならない ということはありませんが、例えば3か月以上国外に滞在している期間があったり、年間で通算100日以上を国外で過ごしているなどの場合には、「継続して日本に住居している」とみなされないことがあるため、注意が必要です。(この「3か月」「100日」も、明確な基準があるわけではなく、過去事例からの大まかな目安です)また、この5年間のうち、おおよそ3年以上は就労系の在留資格で就労していることが求められます。これも、明確な要件・基準が公表されているわけではありませんが、実際には審査にあたってはこのような取扱いがなされているとのことです。ここでの就労には、資格外活動などでのアルバイトや、技能実習、特定技能などは含まれない点が注意です。なお、国籍法6条1項3号により、「引き続き10年以上日本に居所を有する者は、国籍法5条1項1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」とあるのですが、それでも、1年程度の就労実績は必要であるといわれています。
2.18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号)
申請時点で18歳以上であり、母国においても法律上成人していることが必要となります。成人年齢は国によって異なり、日本や中国の場合は18歳ですが、韓国や台湾の場合は20歳、インドネシアやアルゼンチン、エジプトなどは21歳、アメリカ合衆国などでは州によって18歳~25歳と様々です。
3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
この「素行善良」には、明確な基準がありませんが、一般的には、税金や年金・保険料等をきちんと納めていること、前科、犯罪歴、交通違反などがないこと などと言われています。
税金や年金・保険料等の支払については、同居の親族が居る場合、その同居の親族についても正しく納めているか審査されます。また、扶養家族が居る場合、その扶養家族が扶養控除額以上の収入を得ていないか、また、海外の扶養家族が居る場合、その扶養は適正な条件に合致しているかなども審査されるため、注意が必要になります。
交通違反については、軽微な違反が数回程度であれば、審査に大きく響くことはないと考えられますが、飲酒運転、自責での交通事故、スピード違反などで罰金となった場合や、違反を何度も繰り返しているような場合には、これが素行不良として帰化が不許可となる可能性が高くなるため、こうした経歴がある場合には、過去の違反に対する罰金の支払い等を行った後、3年~5年間はこのような問題を発生させることなく、素行善良に過ごした後に、帰化申請を行うことが推奨されます。
なお、この素行善良要件に関しては、過去の犯罪や税金・社会保険等の滞納以外でも、生活全般において何かトラブルが無かったかなども問われるケースがあるため、注意が必要です。たとえ自分自身が悪くない(と思っている)場合でも、例えば交通事故に遭った、誰かとトラブルになり警察の介入を受けたことがあるような場合には、事前に事情を申告しておくことをお勧めします。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
帰化を希望する外国人自身や、同居する親族等の収入によって、生計が成り立つことが要件とされます。具体的な収入額について明記、公開されているわけではありませんが、一般的な目安として、以下のようなことがいわれています。
・申請人1名につき年収300万 扶養家族が1名に対して、+50万
※上記の例の場合、申請人に対して、扶養家族である配偶者が1名と、2名の子供(いずれも同居の被扶養者)がいる場合には、300+50+(50×2)=450万円が、要件を満たす収入額の目安となるでしょう。
この、生計要件は、現時点での資産額というよりは、今後、生活していけるような安定した収入があるか という点で審査されます。そのため、貯金額を多さはあまり関係がなく、むしろ、貯金額を多く見せるために、多額の借金をしたような場合には、マイナス要素としてみられます。また、上記にもあるように、「収入が安定しているか」という点が重要なため、転職したばかりや、転職により収入が下がっている場合には、これもマイナス要素として判断されるため、生活と収入の安定性を維持させることが重要となります。
※ただし、例えば65歳以上などで定年退職し、年金で生活している方のような場合には、ある程度の資産・貯蓄があることが審査のポイントになってくるかもしれません。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
日本国籍を取得するために、本国の国籍を失うことが要件とされます。日本では二重国籍が認められていないためです。この、「本国の国籍を失う」ですが、実際の帰化申請手続きでは、注意する点があります。国によって、「他国籍を取得すると自動的に自国籍が失われる(中国・韓国等)」「事前に国籍の離脱を行わなければならない」「事前に国籍の離脱を行うことができない(ブラジル・フィリピン等)」など、国籍に関する規定が様々となっており、これに応じて、日本での帰化申請にあたって事前に実施すること、事後に実施することが変わってきます。特に、「事前に国籍の離脱を行わなければならない」の場合で、当該国の国籍離脱の手続きに1年~2年程度かかる国もあるため、事前での調査や計画的な帰化手続の準備が必要となります。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法5条1項6号)
・・・要するに、暴力団員や、テロリストに該当すると認められる場合が挙げられます。
国籍法の要件にはありませんが、日本語能力が要件として求められます。日本で日本人として暮らす以上は、一定程度の日本語能力がなければ、日常生活や、権利義務の履行に支障がある という考えによるもとだと思われます。
日本能力は、事前に試験などを受験して試験結果を添付証跡として提出するようなものではなく、実際の帰化の審査の過程において、審査官との面接や、筆記試験によってテストされることになります。概ね、日常レベルの会話や読み書きができる程度(日本語能力試験N4~N3程度)と考えられます。筆記試験では、難しい漢字というよりは、ひらがなやカタカナが正確に書けるかということが試されるようです。
帰化申請では、書類審査の後に、申請人との面接があります。ここでは、提出した申請書類の内容などについて、本人から直接口頭で説明を行い、その内容に矛盾がないかなどを確認することが目的となっています。また、本人以外にも、日本に在住している親族や、配偶者についても、面接の対象となります。(どの範囲までが面接の対象となるかについては、明確な決まりはありません。)面接は、すべて日本語で行われますが、申請対象外の親族の日本語コミュニケーションに不安がある場合には、申請人が通訳として立ち会うことは禁止されていません。
面接のポイントは、申請した内容が真実であるか確かめるために本人から直接話を聞く点にあるため、申請書類と矛盾の無いように、きちんと内容を把握しておくことになります。もちろん、行政書士等のサポートがあった場合でも、申請人本人が申請内容を把握していることは必須ではありますが・・・例えば、今までの細かい経歴(引っ越し歴、職歴)などは、過去のことは書類に起こしたとしても、パッと思い出せないことがあるかもしれませんので、注意しておきましょう。また、当然のことながら、隠し事や嘘は厳禁です。過去の犯罪歴や、在留状況などは、当局に記録があるためわかるようになっています。何か自分に不利な点があったとしても、素直に述べた上で、どうしてそのようなことになったのか、今後同じことを繰り返さないためにどうしているかなどを、真摯に答えるようにしましょう。
なお、面接は申請人本人や、関係親族と1対1で行われるため、他に人のサポートを受けることができませんが、一方で、最終面接前の事前相談や個別相談の場合には、サポートの同席が認められます。(これも、法務局によってルールが異なるため、一概には言えません)事前相談や個別相談の場合には、色々と今後の手続きや必要書類等について説明を受けることがありますが、担当官が何を求めているのか、具体的に何の書類のことを言っているのか、理解が難しい場合もあると思われます。そうした場合に備えて、行政書士などの専門家に同席し、サポートしてもらうのも良いでしょう。
帰化申請における審査官とのやり取りの中で、「現状のままでは厳しいかもしれない」と言われることがあるかもしれません。こうした場合は、申請内容において、何かしらのマイナスポイントを抱えている状況であり、このまま審査を進めても、不許可となる可能性を秘めていることを示唆されています。もちろん、必ず不許可になると決まっているわけではありませんが、「厳しい」というのは、「不許可の確率が高い」という意味になります。この「厳しい」という言葉のニュアンスは、少し難しい日本語かもしれません。こうした場合には、何が「厳しい」のか、具体的には、どういう点で舞いますポイントがあるのか、審査官と良く会話をした上で、ヒントを聞き出すようにしましょう。過去の経歴については変えられない点はありますが、例えば社会保険料の滞納歴があり、その再発防止策が十分でないなど、今後の申請にあたって、対策を講じて、実績を積むことで許可要件を満たせるものもあるかと思います。また、場合によっては、「取り下げてはどうか」と言われることもあるかもしれません。こうした場合も同様に、現状何か問題があるのかを把握した上で、改めて不備や不足を修正した上で、申請を行うのが良いでしょう。
在留資格(帰化申請も同様)における添付資料は、入管庁の規定する所定のものを漏れなく提出すれば良いかというと、そういうものではありません。入管庁が規定しているものは、最低限かつ例示的なものであって、実際の申請にあたっては、申請人の状況において、その必要書類や内容は異なってきます。申請における添付書類というものは、申請人が申請の要件(在留資格該当性、基準省令適合性)を満たしているということを客観的に証明するための証拠として提出するのであって、例え規定の書類名の書類を提出したとしても、その内容では証明したい申請人の適格性が判断できないのであれば、不備・不足ということになります。申請人が証明したい資格(学歴や職歴など)に対して、それが真実である、その書類を見ることで、「資格を満たしていると判断できる」もの それが、本当に必要となる添付書類となるのです。
ご自身で申請しようとした場合、添付資料の集め方でなかなか上手くいかず、不許可となってしまうケースがあるかもしれませんが、行政書士のような専門家は、上記のような視点で、申請人の状況を分析し、必要な証明方法の立案、資料の収集を行うことができますので、一度相談してみるのが良いでしょう。
就労系の在留資格で働いている外国人の方や、留学生、家族滞在として日本に在留している外国人のかたが、本来の在留資格で認められた活動とは別の活動を行いたいという場合、「資格外活動許可」を得る必要があります。一般的な例では、留学生や家族滞在の外国人が、アルバイトをするようなケースです。資格外活動の許可を得ずに、アルバイト等を行うことはできません。また、資格外活動は、どんな仕事でも、時間無制限でできるわけではありません。風俗営業関連は認められないことと、労働時間についても、1週間で28時間を超えて働くことはできません。この「1週間で28時間」については、1週間のどこで数えても合計28時間を超えてはいけないため、例えば土曜日~月曜日で30時間働き(毎日10時間)、火曜日~金曜日までお休み・・・というパターンはNGになりますので、ご注意ください。
※上記は「包括許可」と呼ばれる場合の制限ですが、これとは別に「個別許可」というものがあり、個別許可の場合には1週間の労働時間の制限はありません。また、学校の夏休み期間などの場合には、1日8時間、週40時間までと、労働時間の上限が拡大されます。
許可の内容が包括許可なのか、個別許可なのかにより、労働時間の制限が異なりますが、特に包括許可の場合には、1週間に28時間を超えないように、働く側と、雇用する側は十分に注意する必要があります。また、「風俗営業関連」についても、例えばゲームセンターやパチンコ店、麻雀店なども、これに該当しますので、注意が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が認められるポイントとして、「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもの」「学歴と従事する業務の関連性があること」「相当の業務量があること」が要件となっています。大学を卒業した場合には、大学の卒業していることで、「技術・人文知識・国際業務」との関連性は認められやすいのですが、専門学校を卒業した場合には、専門学校で学んだ内容と、従事しようとしている業務の関連性が強く求められます。
まずは実際に、「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない」とされた事例として、次のようなものがあります。
①ベンチャービジネス学科を卒業した人が、オートバイの修理・改造・輸出入の業務に従事するとして申請を行いましたが、実際には、フレームの修理や、パンクしたタイヤの修理業務などにとどまるため、この業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない とした事例
②国際情報ビジネス科を卒業した人が、中古電子製品の輸出・販売等に従事するとして申請を行いましたが、実際には、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等にとどまる仕事であったため、この業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない とした事例
③「翻訳・通訳業務に従事する」として申請を行いましたが、実際には、小売店の接客販売員であったため、認められないとされた事例
その他、比較的単純労働であったり、繰り返すことで誰でも習得可能な業務に従事しようとする場合は、それは「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもの」とは認められない となる可能性が高いです。
次に、「学歴と従事する業務の関連性が認められない」とされた事例について、次のようなものがあります。
①声優学科を卒業した人が、外国人が多く訪れるホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請を行いましたが、学歴と業務に関連性がないとして、認められなかった事例。
②イラストレーション科を卒業した人が、外国人が多く訪れる衣料品販売店の店舗スタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請を行いましたが、学歴と業務に関連性がないとして、認められなかった事例。
③国際ビジネス学科で、英語を中心に、パソコン、簿記、貿易・経営業務等を履修した人が、不動産業(アパート賃貸)の営業に従事するとして申請を行いましたが、先行した科目と業務に関連性がないとして、認められなかった事例。
外国語を生かした業務であるか、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務であるかという点だけではなく、学歴(専攻科目)と、業務との間に、関連性があることが必要になります。
その他、「相当の業務量があること」も要件の一つとなります。例えば、「店舗において翻訳・通訳業務に従事する」として申請する場合、その店舗で、どれだけ翻訳・通訳が必要となるシーンがあるか?という点です。飲食店において、単に英語で注文を取る、メニュー表の日本語を英語に翻訳する程度では、業務として日常的に翻訳・通訳を行っているとは認められないでしょう。(大半の時間が、翻訳・通訳を必要としない店舗スタッフとしての業務に割かれていることになります。)またそもそも、外国人が訪れる機会が多いとは言えないような店舗、サービスにおいては、翻訳・通訳の必要性・業務量が存在するとは言えないでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかの判断、ご自身が従事したい業務と、ご自身の学歴との関連性について不安な点がある場合には、一度専門家に相談してみるのが良いでしょう。(※実際の審査については、出入国在留管理局の審査官が行うため、行政書士等の専門家に相談した結果の通りになる保証はないという点について、ご留意願います。)
特定技能は、労働力の不足している特定産業分野について、外国労働者の雇用によってその労働力不足を補う目的で2019年に創設された在留資格です。特定技能で雇用することのできる産業分野は限られており、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野となっています。この16分野に属する産業であれば、外国人労働者を雇って従事させることが可能かというと、雇用される外国人、雇用する側の事業者で、様々な条件をクリアする必要があります。
<外国人側の要件>
従事しようとする仕事に関して、一定の知識・技能を有していることが要件となります。具体的には、その知識・技能を証明する試験に合格するか、技能実習を良好に終了していることの証明が必要になります。また、従事しようとする業務の知識・技術のみでなく、一定の日本語能力も求められることになります。
<事業者側の要件>
外国人の受入体制の整備が必要になります。「支援計画」を作成して、支援計画の内容に則った運営を行うことが必要となります。この支援については、自社ですべての支援を行うことが難しい場合には、登録支援機関という外部機関に委託することも可能です。支援の内容は、空港への送迎や、日本で就労・生活する上でのオリエンテーション、相談・苦情対応、定期的な面談など、様々なものがあります。また、特定技能外国人を受け入れようとする事業者には、過去に、入管法、労働関連法の違反がないこと、非自発的離職者が居ないこと(会社都合での解雇がないこと(外国人に限らず日本人に対しても))などの要件が求められ、これらの要件を満たしていない場合には、特定技能外国人を雇用することはできない上、もし違反が発覚した場合には、雇用している外国人を離職させなければならなくなります。
初めて特定技能外国人を雇用しようとする事業者においては、上記のような様々なハードルがあると思われます。また、実績のある事業者でも、細かい法令や運用規定まで追いきることは難しく、気が付かないうちに法令違反となってしまうという可能性も考えられます。外国人雇用の中でも制度が複雑で難しい「特定技能」や「技能実習」を行いたい場合には、専門家に相談しながら進めるのが良いでしょう。
高度専門職ビザをお持ちの方が転職する際に必要となる手続きについて解説します。
一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の場合、入国管理局で新たな在留資格を取得する必要はなく、変更申請も不要です。転職後14日以内に「所属機関変更の届出」を行うだけで手続きは完了します。この届出は審査が行われるものではなく、即日完了するのが通常です。
一方で、高度専門職ビザをお持ちの方が転職する場合、通常は「在留資格変更許可申請」が必要となります。これは、高度専門職ビザが申請人と雇用先の会社をセットで審査する仕組みに基づいているためです。
高度専門職ビザの場合、パスポートに「指定書」がクリップやホチキスで留められています。この指定書には、氏名や国籍、許可の分類(例:1号ロ)、および許可を取得した際に雇用契約していた会社の名前が記載されています。つまり、高度専門職ビザで就労可能な場所は特定の会社と紐づいており、転職によりその紐づけが解消される場合には、現在のビザをそのまま使用することができません。
したがって、転職の際に現在お勤めの会社を辞めると今お持ちの高度専門職ビザはその許可された根拠を失うため、そのまま新しい勤務先で使い続けることができず、何かしら別の在留資格への変更申請が必要になります。
「高度専門職1号」保持者が転職する場合、所属機関変更の在留資格変更許可申請が必須で、新職務でも70点以上を維持せねばなりません。一方、「高度専門職2号」なら転職時の変更申請は不要ですが、専門職活動の継続は必要です。双方とも6ヶ月以上の活動停止は資格取消に繋がります。
まず、「家族滞在」ビザにおける配偶者は、現に法律上有効な婚姻をいいますが、ここには、外国で成立した同性婚の婚姻は、例えそれがその国では法律上有効であったとしても、家族滞在としては認められません。一方で、このように外国では有効に成立している同性婚者については、人道的観点から、「特定活動」での在留が認められる可能性はあります。ただしその場合の条件として、以下のようなものがあげられます。
①二人のうち片方がもう片方の扶養を受けて同居すること
②二人のうちいずれかが、日本において本件特定活動以外の在留資格で在留していること、言い換えると、日本において何らかの在留資格によって長期に滞在する状況であること。(二人とも本件の特定活動で在留するということはできない)
③二人とも、自分の国において同性婚が有効に認められていること。この③の要件によると、同性婚による特定活動が認められるのは、二人とも外国人である場合に限られることなります。なぜなら、日本においては同性婚が有効に(法的に)認められていないため、自ずと、自国において同性婚が認められている外国人同士ということになるのです。
留学生が日本人と結婚し、在留資格を「留学」から「日本人配偶者」へ変更したいという場合の注意点です。在留資格が「留学」ということは、何かしらの学校(大学・専門学校等)へ在籍していることが想定されますが、ここから「日本人配偶者」へ在留資格の変更を行う場合には、次のようなケースが考えられます。
①学校へ在籍したまま在留資格を「日本人配偶者」へ変更する。
②学校を卒業した後に、在留資格を「日本人配偶者」へ変更する。
③学校を退学し、在留資格を「日本人配偶者」へ変更する。
上記のケースで、②については問題がないと考えられますが、特に③のケースでは、審査が厳しくなるものと考えられます。というのも、本来留学の在留資格は、日本の学校に通った上で、学業を全うし卒業するということが目的であり、在留資格の本質的な要件になっているものであり、卒業をしないまま、在留資格の変更を行うという行為に対しては、「では当初の留学の目的は何だったのか? 真に留学をして学業を修めるという意思はあったのか?」と問われてしまう結果となります。そのため、留学から、別の在留資格へ変更することは、本来は好ましいことではありません。このようなケースでは、留学から日本人配偶者への変更を行うことについて、やむを得ない理由ないし合理的な理由があるということについて、理由書などできちんと説明を行う必要があります。
外国人配偶者の子供(連れ子)が外国におり、日本に呼び寄せたいという場合には、一定の要件を満たすことで、「定住者」の在留資格を得て、日本に住むことができるようになります。この場合の一定の要件として、子供が未成年であること、未婚であることなどがあげられます。子供が一定年齢以上・・・20歳程度で、就労可能な年齢に達しているような場合には、自分で生活することができ、養育する必要がないということから、認められずらくなります。
また、外国に住む外国人配偶者の親を日本に呼び寄せたいという場合、実はこれに該当する在留資格は存在せず、特別な許可「特定活動」での申請をすることになります。さらに、認められるための条件として、以下のような条件に該当することが必要とされています。(※特定活動は、いずれの在留資格にも該当しない場合に、法務大臣が個々に活動を指定するものになります。このケースもそのうちの一つであって、必ずしも条件が明確に定められているわけではない点に留意が必要です。)
①親が外国で1人で暮らしており、配偶者、兄弟等も含めて、誰も面倒をみることができる親族がおらず、日本に居る外国人配偶者が唯一の親族であるような状態であること
②親の年齢が70歳以上であること
③その他、親を監護(扶養)できる程度の収入があること 等
上記の3点をクリアしたとしても、必ずしも認められるとは限らず、個々の事情を踏まえた上で判断がされることになります。どうしても日本に呼び寄せて一緒に暮らさなければならない、暮らしていけるという点について、その証拠とともに、細かく事情を説明することが必要になります。