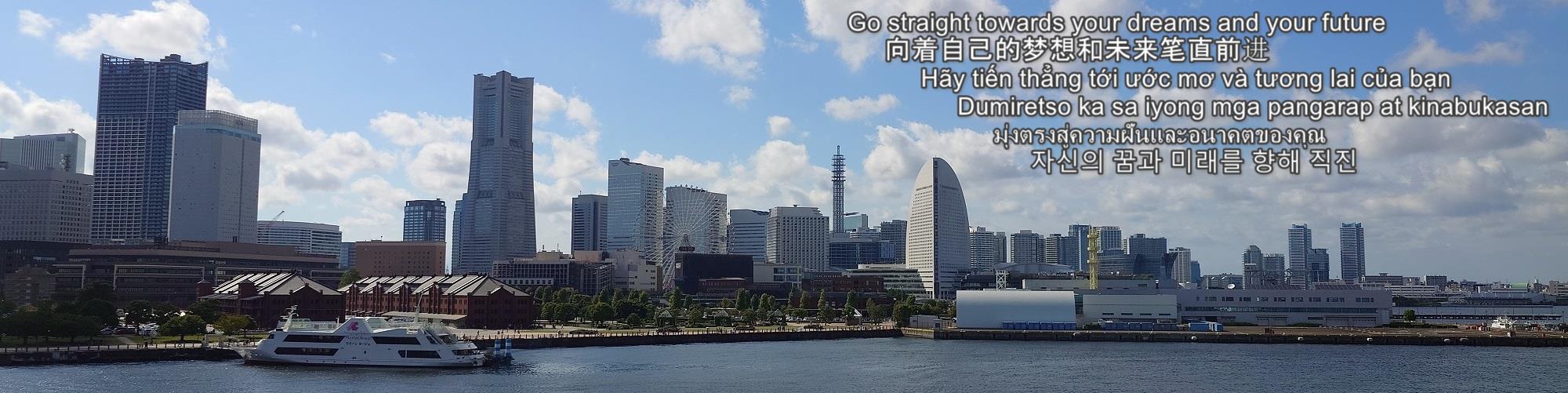クリエイター支援
エンターテインメント業界の契約や許認可は独自のルールや慣習があり、一般的な法務知識だけでは対応が難しい場合があります。エンターテインメント分野に精通する行政書士が、美術・漫画・アニメ―ション・映画・音楽・ゲーム・イベント運営などの領域で必要な各種手続きをでサポートし、クリエイターの皆様の、創作活動やビジネスの円滑な展開を実現します。
主な取り扱い業務
- 著作権に関するご相談、セミナー
- 創作、出演、著作権に関する契約書作成
- 各種利用規約の作成
- 著作権許諾代行手続
- 文化庁への各種著作権登録業務
- 補助金・助成金申請
著作権法では、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著2条1項1号)」と定義されています。
<思想または感情>
「思想または感情」とは、人間の「考え」「気持ち」「意見」「感情」などの、内面的・精神的なものをいいます。こうした人間の内面・精神から生まれたものが、著作物となります。人間の内面・精神から生まれたものではない、単なる事実の伝達であったり、客観的な事実やデータそのもの、そもそも人間が製作したものでないものは、「著作物」とならず、著作権法の保護対象外になります。
生成AIによる作品が著作物に該当するか、近年の議論となっています。基本的には、人間が作成したものではない(人間の創作性がない)ため、著作権法における著作物に該当しないという見解もありますが、人間がAIに与えるプロンプトにある程度の創作性(具体的かつ詳細な指示)が認められる場合には、AIによる生成物も著作物と認められる可能性はあります。
著作物を創作すると、著作者には著作人格権と著作(財産)権が自動的に発生します。何処か役所(例えば文化庁?)などへ登録申請したり、誰か(創作の依頼者?出版社?)と契約することで発生するものでありません。これを「無方式主義」といいます。
著作権の存続期間(保護期間)は、原則として著作物の創作時~著作者の死後70年を経過すると消滅します。「消滅する」とは、文字通り著作権がなくなることを意味し、権利が消滅した著作物は、自由に利用することができるようになります。例えば、存命中の作曲家の音楽を無断で演奏してはなりませんが、モーツァルト(1791年没)の曲は、自由に演奏しても良いことになります。
著作権は所有権と同じように、他社に譲渡することができます。著作権の譲渡自体は、契約をすることで、その効力が発生しますが、登録を行わなければ、第三者に対抗することができない と規定されています。
<「登録」とは?>
文化庁に、『これこれこういう作品の著作権を、Aから、B社へ譲渡しましたので宜しく』という届出を出すことです。基本的には、著作権を譲り渡す側(Aさん)と、譲り受ける側(B社)と共同で行うものであり、片方だけで勝手に行うことはできません。自分自身で実施することも可能ですが、専門家である行政書士、弁護士、弁理士などで行うことができます。
<登録しないとどうなる? 「第三者に対抗することができない」とは?>
Q:漫画家のAさんが、自分の作品の著作権を、B社に譲渡する契約をしました。その後、Aさんは、C社に対しても、その作品の著作権を譲渡する契約をしました。また、C社は、この著作権の譲渡について、著作権を譲渡したことの登録をしました。そして、C社がこの作品を本にして出版していたところ、B社から、『うちの方が先に契約したのだから、うちが著作権を持っていて、出版する権利がある。なので、C社は出版を止めてくれ!』といってきた。この場合、C社は出版を止めなければならないのか、B社は出版することができるでしょうか?
A:C社は出版を止める必要はなく、B社は何も言えません。つまり、登録したC社の勝ちです。登録を行わなかったB社は、C社に対抗・・・つまり、勝ことができない ということです。
著作権には、様々な登録制度があります。
|
著作権・著作隣接権の移転等の登録 |
著作権もしくは著作隣接権の譲渡、信託、質権設定があった場合、登録することで第三者対抗要件を備える。 |
|
出版権の設定の登録 |
出版権の設定、移転、質権設定があった場合、登録することで第三者対抗要件を備える。(※実際にはあまり利用されていないようです。登録料がかかることと、登録を行わなくても、契約自体は成立し、実際に問題になることがないためだそうです。) |
|
実名の登録 |
無名または変名で公表した著作物の著作者は、実名の登録ができる。登録をした者が著作物の著作者であると推定を受けられる。この登録をすると保護期間が、公表後起算から死後起算になる。 |
|
第一発行年月日等の登録 |
その日に最初の発行(公表)があったものとの推定を受けられる。 |
|
創作年月日の登録 |
プログラムの著作物について創作年月日の登録ができる。 |
文芸や学術、美術、音楽などの「文化」に所属するものが著作物となります。一方で、量産が可能な工業製品のようなものは、「産業・工業」に属することになり、「文化」に属するものとは言えません。例えば自動車などの工業製品のデザインは、工業的に全く同じものを量産できるため、文化の範囲に属するとは考えられず、著作権法の保護対象外となります。
※自動車のような工業品は、「意匠法」で保護されます。
※意匠法:物の形状や模様、色彩を保護する法律
では、漫画に、実在の車を登場させることは、意匠法で問題とならないでしょうか?
漫画に、実在の車を登場させることは、意匠法上は違法にならないと考えられます。意匠法は、「同じような形で、同じような物品を作っては駄目ですよ」という法律のため、形が似た自動車を無断で製造することはできませんが、漫画に描くということは、次元(物品)が異なるため、禁止範囲に入りません。ただし、何を参考にこれを描くか という問題があります。もし、他の人が撮影した自動車の写真などを、その写真を撮影した人に無断で参考にして、自動車の絵を描いた場合には(写真の構図の通りに描く場合を想定)、写真を撮影した人の著作権を侵害することになります。そのため、何か実在のものを参考資料とする場合には、自分自身で撮影するのが無難です。
キャラクターや世界観、キャラクター名、商品名は、著作物とはなりません。ただし、商標法や不正競争防止法で保護される可能性があります。(言い換えると、無断利用は認められません)
※商標法:商品やサービスに付けるマークや名前を保護する法律
※不正競争防止法:無断で他人の商品名や商品の形を真似することを禁止する法律
名称・設定・世界観については通常は著作物としては保護されません。こうしたものの取扱いについて、創作の契約を行う際に明確にしておくためには、契約書などで「名称も著作物として扱い、二次利用時は協議または許諾を要する」のように明示するのが確実です。
また、特にヒット作品などについては、そのタイトルやキャラクター名、特徴的なセリフまでもが、関係ない第三者によって商標登録されるという問題が発生しています。そのため、こうした「著作物ではないが、経済的に価値のあるもの」については、商標登録などの検討を行い、関係ない第三者による不正利用を防止する という点についても、意識しておくと良いと考えられます。